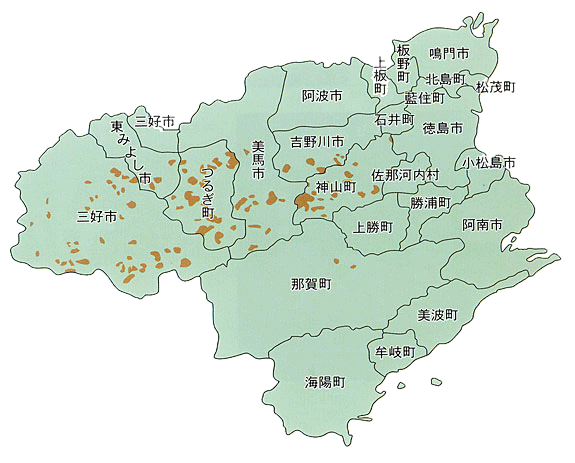| 地すべりの概要
徳島県は、西日本屈指の地すべり多発県であり、殆ど全県下にわたって地すべり指定区域がみとめられる。林野庁所管地すべり防止区域として133地区が指定されている。これは、東西性の次元の高い断層破砕帯が通っていることが、1つの大きな原因となっているが、規模の大きさ、継続性という観点からみた場合、真の地すべりがみられるのは、三波川帯、及び御荷鉾帯のみといってよい。他の帯では多くの場合、崩壊、又は崖錐の落下によるものが大部分で、豪雨、又は長雨の誘因が大きい。
和泉帯では、崩壊の多いのは断層に近接した地域、或は流れ盤となって谷に層廟が傾斜している所などが多く、特に阿讃山麓部では、中央構造線に、fそ行又は斜交する断剛二よる崩壊が若しい。
秩父帯では中帯に崩壊が集中している。 これは、坂州衝仁、巨 二社衝卜の 二本の断層が大きく左右していること、及び古生屑・中生層の間に存在する断層も影背を及ぼしたものであろう。
四万十帯においては、殆ど指定地域がみられないが、それでも、椿-星越断層、深瀬一伊座利断層に沿っては崩壊がみられ、県の南端でも同様に断柳二桁うものがみられる。
三波川帯、御荷鉾帯では断層運動によって岩盤が破砕され、地すべりをおこしている。したがって地すべり地の分布と地質構造との間に密接な関係がある。
点紋帯の岩石は風化に対する抵抗が、無点紋帯の岩石より弱く、地表に近い岩石は風化されて土状となっている。したがって崩壊性またはクリープ性の動きをしめす小規模な地すべりがある。無点紋帯の岩石は菓片状に剥離する性質があり、とくに泥質片岩を断層破砕帯が通る場合、鱗片状に破砕されて砂質の粘着性のない崩積土を生じている。地すべり運動は局地的に不規則で、同じ地域のなかでも特に動きのはげしい部分と全く動かない部分とが混在している。
御荷鉾帯の地すべりは、日本列島という規模での大きな断層(みかぶ線)にそっておこっている。断層破砕帯は明瞭で、泥質片岩とみかぶ型緑色岩類が接する部分で、両方の岩石が幅0〜3.Okmにわたり破砕されている。断層が大規模なものであるので、地すべり運動も広汎で、しかもほぼ均一一に地域全体が動いている。時として急激でしかも大きな動きを示すので、この帯の地すべりが最も危険である。
|